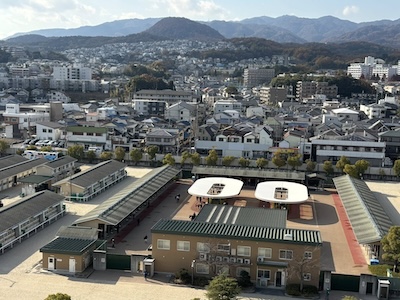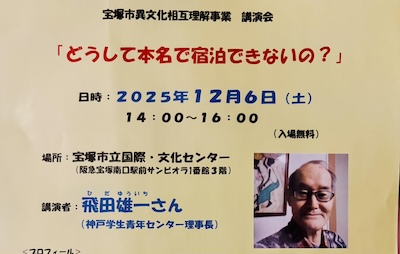活動日誌
| ・北野さと子の毎日をご報告。 ・日々、感じたことを書いていきます。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Topics Board -